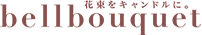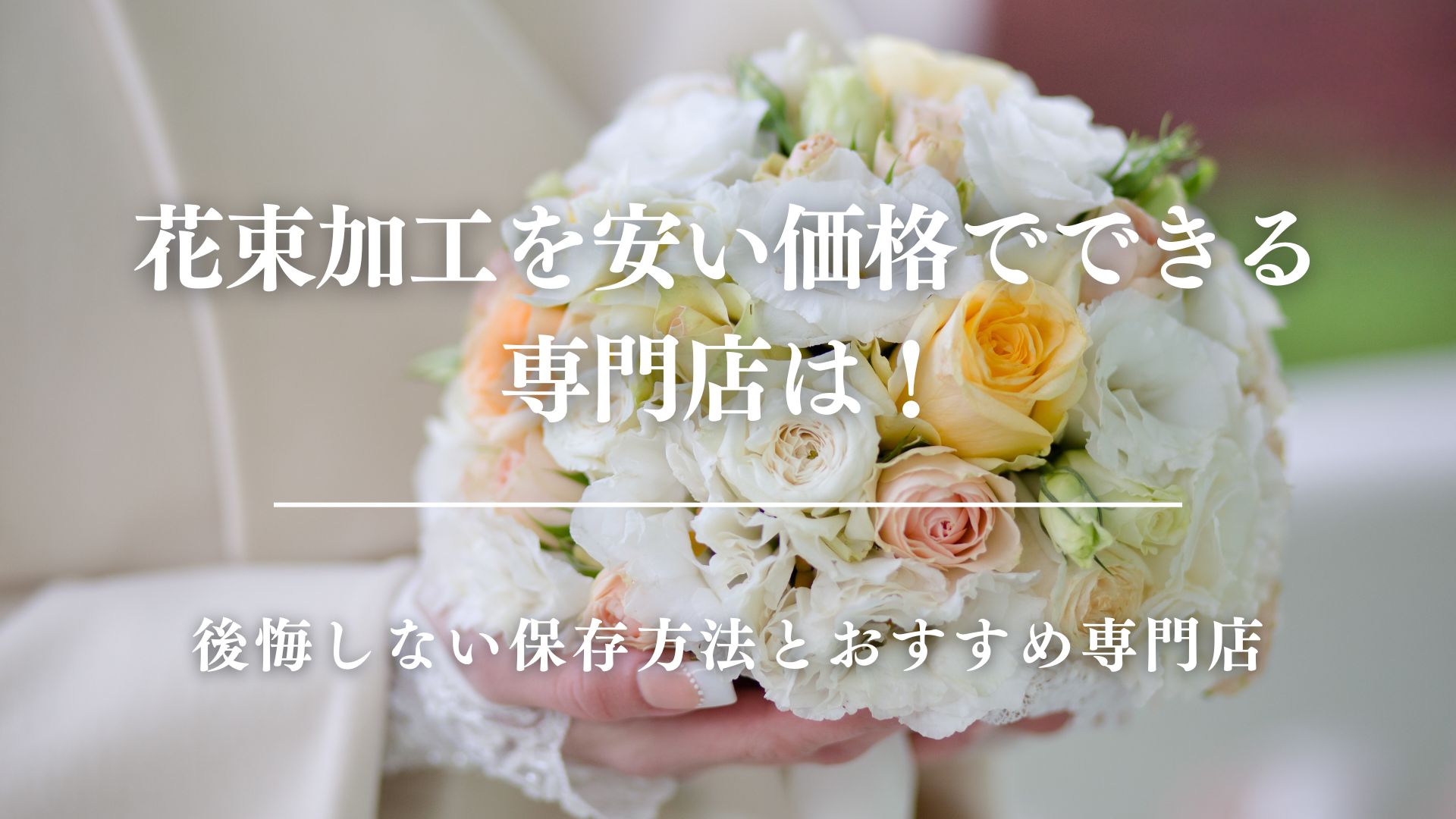【2025年最新版】入籍後に必要な手続き・届け出・やることリストを総まとめ

「入籍後って、具体的に何から始めればいいの?」
そんな不安や疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。手続きや報告、今後の準備までやることが多く、つい後回しにしてしまいがちです。
この記事では、
- 入籍後にやるべき手続きや届け出の全体像
- 平日にしかできない手続きと、ネットで完結できるものの違い
- 家族や職場、友人へのスマートな報告方法
- 結婚式や新婚旅行、今後のライフプランの考え方
- 記念として残したい「思い出の花」の活用方法
について詳しく解説します。
最後には、特に注目されているアフターブーケの新しい形『ブーケキャンドル』についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
大切なブーケを”一生の思い出”
に残す方法をご存じですか?
👰「結婚式で使ったブーケ、捨てるのはもったいない…」
💐「大切な花束を、形として長く残していたい…」
😭「料金や保存期間が心配だけど、どこに相談したらいいかわからない…」
ブーケは結婚式の思い出そのもの。でも、「どこに頼めばいい?」「デザインは?」「費用は?」など不安はつきものですよね。

bellbouquet(ベルブーケ)は、累計2,000本以上の花嫁様の“アフターブーケ”をサポートしてきたアフターブーケキャンドル専門店です。
今なら公式LINEにご登録いただくだけで、「あなたのイメージに合うアフターブーケキャンドルとお見積り」を無料でご案内!
さらに、本記事限定で、「3,000円OFFクーポン」 をプレゼント中!
結婚式の大切な想い出を、“美しく、永く” 残してみませんか?

- 入籍後にやるべきこととは?まずやることリストの全体像を把握しよう
- 入籍後のやることリストは“平日にしかできない”ものと“いつでもできる”もので分けよう
- 平日1日しか休めない人向け|1日で終わらせる入籍後やることリストスケジュール例
- 入籍後やることリスト①|【役所・公的手続き】で必要な項目
- 入籍後やることリスト②|【勤務先での手続き】も忘れずに
- 入籍後やることリスト③|【家族・親戚・友人】への挨拶や報告
- 入籍後やることリスト④|【引っ越しに関する手続き】をスムーズに
- 入籍後やることリスト⑤|【氏名・住所変更が必要な民間サービスの手続き】
- 入籍後やることリスト⑥|【今後の準備・ライフプラン】も忘れずに
- 入籍後やることリスト⑦|結婚式は入籍前?後?ベストなタイミングとは
- 入籍後の思い出を残すなら?bellbouquet(ベルブーケ)という選択
- まとめ:入籍後のやることを知って、スムーズな新生活を
入籍後にやるべきこととは?まずやることリストの全体像を把握しよう

入籍後は、結婚式や引っ越しのタイミングも関係して、やるべきことが一気に増えていきます。
まずはどんな手続きや対応があるのか、全体像を把握することが大切です。
手続き・挨拶・ライフイベントなどを整理しながら、進める順番やタイミングの目安を確認していきましょう。
入籍日とは?結婚式や引っ越しとの関係
入籍日とは、婚姻届が役所に受理された日を指し、この日から法律上の夫婦として認められます。
希望する日がある場合は、その日に婚姻届が受理されるようにスケジュールを調整することが大切です。
結婚式や引っ越しとの関係についても、入籍日との兼ね合いを考えておくとスムーズです。
入籍日と結婚式のタイミング
- 結婚式より前に入籍するカップルが多い
→ 縁起の良い日(大安など)を選んで先に入籍 - 結婚式当日を入籍日にする人も
→ 書類提出ができるかどうか要確認(役所の開庁日かどうか)
入籍日と引っ越しの関係
- 入籍前に引っ越す場合
→ 婚姻届に新住所を書くことになるため、住民票の手続きもセットで進めやすい - 入籍後に引っ越す場合
→ 転入・転出届などが別タイミングになるため、手続きの回数が増える可能性も
入籍・結婚式・引っ越しはそれぞれの手続きに影響し合うため、あらかじめスケジュールを整理しておくと、余計な手間を減らせます。
入籍後やることリストの全体像【手続き・挨拶・準備ごと】
入籍後にはさまざまな手続きや対応が必要になりますが、まずは全体像を把握することが大切です。やることは大きく以下の3つに分類できます。
① 公的・民間の各種手続き
- 役所への届け出(住所変更、保険・年金、マイナンバーなど)
- 勤務先での手続き(扶養の申請、名刺や書類の変更など)
- 免許証や銀行口座、パスポートなどの名義変更
- クレジットカードや携帯電話など民間サービスの情報更新
② 挨拶・報告まわり
- 家族や親戚への報告・挨拶
- 友人・知人へのお知らせ
- 年賀状や報告はがきなどの準備
③ 今後に向けた準備
- 結婚式や新婚旅行のスケジュール調整
- 新居への引っ越しとライフラインの契約変更
- ライフプランの話し合い(妊活・仕事・貯金など)
手続きのなかには平日でないと対応できないものもあり、優先順位を決めて計画的に進めることがポイントです。
一度にすべてを完了させるのは難しいため、できることから段階的に取り組むようにしましょう。
入籍後やることリスト、それぞれのタイミングは?
入籍後の手続きは多岐にわたりますが、すべてを一度に行うのは現実的ではありません。
そこで、いつまでに何をやればいいのかというタイミング感を把握しておくことが大切です。
入籍後すぐに対応したいもの(当日〜1週間以内)
- 婚姻届の提出と受理の確認
- 役所での住所変更や世帯変更の届け出
- 勤務先への結婚報告と必要書類の提出(保険・扶養など)
余裕をもって進めたいもの(2週間〜1ヶ月以内)
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの名義変更
- 銀行・保険・クレジットカードなど民間手続きの更新
- ライフライン・携帯・通販サイトなどの登録情報変更
タイミングを見て進めるもの(1ヶ月以降でもOK)
- 結婚式や新婚旅行の準備
- 家族や友人への報告(年賀状やお知らせなど)
- 妊活・仕事・お金など今後のライフプランの話し合い
手続きの中には期限があるもの(転入届は14日以内など)もあるため、カレンダーやリストで管理しながら進めるのがおすすめです。
入籍後のやることリストは“平日にしかできない”ものと“いつでもできる”もので分けよう

入籍後に必要な手続きの中には、「平日の日中にしか対応できないもの」と「ネットや郵送でいつでも進められるもの」があります。
効率よく進めるためには、この2つを切り分けて考えることが重要です。
限られた時間を有効に使うために、優先順位やスケジュールの組み方も押さえておきましょう。
平日にしかできない手続き一覧(役所・警察署・職場など)
入籍後に必要な手続きの中には、平日の日中しか対応できないものが多くあります。
休みを取る必要がある場合もあるため、優先順位とスケジュールをあらかじめ整理しておくことが大切です。
以下は、平日にしかできない主な手続きの一覧です。
役所での手続き(市区町村役場)
- 転出・転入・転居届の提出
- 世帯主変更や世帯合併の手続き
- 国民健康保険・年金の加入や変更
- マイナンバーカードの住所・氏名変更
- 印鑑登録の変更(必要な場合)
警察署・運転免許センター
- 運転免許証の氏名・住所変更(本人が出向く必要あり)
勤務先での対応
- 扶養申請・結婚報告の書類提出
- 名義変更に伴う社内システムや書類の更新
- 健康保険の加入・変更申請
これらの手続きは、窓口が平日9:00~17:00などに限られているため、事前に必要書類を揃えておくことで、当日の所要時間を短縮できます。
土日や平日夜でもできる手続き一覧(ネット・郵送・窓口以外)
平日の日中に役所へ行くのが難しい場合でも、ネットや郵送で対応できる手続きをうまく活用すれば、負担を減らすことができます。
時間に制限されず進められるものを把握しておくと、効率的に対応できます。
ネットやアプリで完結できるもの
- 銀行口座の住所・名義変更(一部金融機関で対応)
- クレジットカードの名義・住所変更
- 通販サイト(Amazon・楽天など)の登録情報変更
- 携帯電話会社の契約者情報の変更(オンライン手続き可)
- NHK、電力会社、ガス会社などの契約情報変更
郵送で対応できるもの
- パスポートの氏名変更(書類の事前取り寄せと郵送)
- 民間保険会社への名義・住所変更届の提出
- 各種サービスへの変更届出書の郵送対応(事前問い合わせが必要)
これらの手続きは、自宅からスマホやPCで対応できるものが多く、スキマ時間や週末を活用できるのがメリットです。
ただし、手続き完了までに日数がかかるものもあるため、早めに取り掛かっておくのがおすすめです。
やることリストの優先度を見極めるコツ
入籍後の手続きは種類が多く、すべてを一気にこなすのは現実的ではありません。
限られた時間の中で効率よく進めるには、手続きの優先度を見極めることが大切です。以下のポイントを参考にして、優先順位をつけて進めましょう。
① 期限があるものを最優先
- 転出・転入届:引っ越し後14日以内
- 扶養申請:提出が遅れると保険適用が遅れることも
- 健康保険・年金の変更:住所・氏名変更後、速やかに申請が必要
② 名義変更が連動するものはまとめて
たとえば、マイナンバーカードの変更を先に行っておくと、銀行口座や保険の変更時に身分証として使えます。
身分証明書の名義変更を先に済ませておくとスムーズです。
③ 平日にしかできない手続きは計画的に
役所や警察署での手続きは、休みを取る必要がある場合も。一日にまとめて複数の手続きを済ませる計画を立てると効率的です。
④ 忘れがちな民間サービスもチェック
携帯会社や通販サイト、サブスクなどは後回しになりがちですが、本人確認や支払いトラブルを避けるためにも早めの対応がおすすめです。
優先順位を把握し、カレンダーやチェックリストで管理すると、抜け漏れのないスムーズな手続きが実現できます。
平日1日しか休めない人向け|1日で終わらせる入籍後やることリストスケジュール例
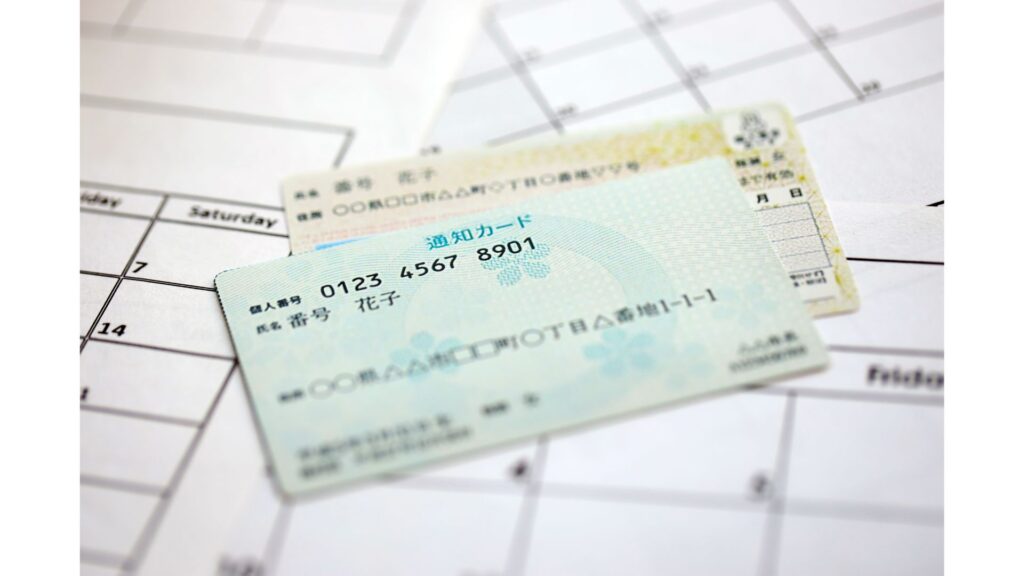
平日になかなか時間が取れない人にとって、入籍後の手続きを1日でまとめて済ませるのは大きな課題です。
限られた時間を有効に使うには、やるべきことを時間帯ごとに整理しておくことが重要です。
このセクションでは、午前・午後・夜と分けて、効率よく進めるスケジュールの立て方を紹介します。
午前中にやるべき役所関連の手続き
平日1日だけ休みが取れる場合、手続きは午前・午後に分けて効率よく進めるのがポイントです。
特に役所関連の手続きは混雑する前の午前中にまとめて済ませるのがおすすめです。
午前中に済ませたい手続き一覧
- 転出届・転入届・転居届の提出
→ 住民票の住所を変更する際に必要 - 世帯変更(世帯合併・世帯主変更)の届け出
→ 結婚に伴って世帯を一つにまとめる手続き - マイナンバーカードの住所・氏名変更
→ 他の名義変更にも使えるため、早めに対応すると便利 - 国民健康保険・国民年金の加入・変更
→ 勤務先の保険でない人は特に重要 - 印鑑登録の変更や抹消(必要に応じて)
スムーズに進めるためのポイント
- あらかじめ必要書類を確認・準備しておく
- 窓口の混雑を避けるため、受付開始時間(8:30〜9:00)に到着するのが理想
- 同じ庁舎内で複数の窓口を回る必要があるため、順路を確認しておくと時短に
役所関連の手続きは、1箇所で複数の届け出ができるケースも多いため、無駄なく進められるように段取りを整えておきましょう。
昼以降に済ませられる免許・銀行・保険の処理
午前中に役所での手続きを済ませたあとは、午後の時間を使って免許証や銀行、保険関連の名義・住所変更を進めていきましょう。
これらは混雑する時間帯を避けることで、待ち時間を短縮できることもあります。
午後に対応しやすい手続き一覧
- 運転免許証の住所・氏名変更(警察署または運転免許センター)
→ 身分証明書としても使うため、早めの対応がベスト - 銀行口座の名義・住所変更(金融機関の窓口)
→ 通帳・キャッシュカード・本人確認書類を持参 - 民間保険(生命保険・医療保険など)の名義変更
→ 郵送でも可能な場合があるが、窓口での手続きが早い場合も - クレジットカード会社への名義・住所変更(電話・窓口)
効率よく回るコツ
- 金融機関は15時に窓口が閉まることが多いため、早めに動くのが基本
- 同一ビルやエリア内に複数の手続きを集約できると、時間短縮に
- 手続きに使う書類(住民票・婚姻受理証明書など)を事前にまとめて持参する
午後は役所に比べて比較的混雑が落ち着く時間帯。待ち時間の少ない窓口を狙って、無理なくこなせるようスケジュールを立てましょう。
夜や週末にまわせる手続きを把握しておく
平日に時間が取れない場合でも、夜間や週末に進められる手続きを把握しておけば、無理なく対応できます。
特にオンライン対応が可能なものや、郵送で完結するものは、平日の負担を軽減する助けになります。
オンライン・夜間・週末対応の手続き例
- 通販サイトやオンラインサービスの登録情報変更
→ Amazon・楽天・サブスクサービスなどは24時間対応 - 携帯電話会社の契約者情報変更(Web手続き)
→ docomo・au・ソフトバンク等、マイページで対応可能 - クレジットカードの名義・住所変更
→ 多くのカード会社が会員ページから手続き可能 - 引っ越し関連の連絡(電気・ガス・水道・NHKなど)
→ ネットでの申請が可能な場合が多い - 郵便物の転送届提出(日本郵便のWeb)
→ 365日・24時間受付可
郵送で対応できるもの
- 民間保険の名義変更申請
- パスポートの切り替え申請書の取り寄せ・送付
- 勤務先への書類提出(郵送指定がある場合)
夜や週末でも対応できる手続きは、まとまった時間が取れない人にとって強い味方です。
先延ばしになりがちな項目も、少しずつ進めておくことで、後の手続きがぐっとラクになります。
入籍後やることリスト①|【役所・公的手続き】で必要な項目

入籍後は、住所や氏名の変更にともない、役所でのさまざまな公的手続きが必要になります。
住民票や世帯変更、保険・年金・マイナンバーの変更など、どれも早めに対応しておきたい重要な項目です。
ここでは、役所で行うべき主な手続きとその流れについて、項目ごとに詳しく解説します。
入籍後やることリスト①|住所変更・世帯変更に関する手続き(転入届)
結婚を機に新居へ引っ越す場合は、住所変更と世帯変更の手続きが必要になります。
これらは役所で行う公的手続きで、期限が決まっているものもあるため、早めの対応が重要です。
主な手続き内容
- 転入届・転居届の提出
→ 引っ越し後14日以内に、転入先の市区町村役場で提出 - 世帯変更の届け出
→ 世帯主をどちらにするかを決め、必要に応じて「世帯合併」や「世帯主変更」の手続きを行う - 住民票の発行・記載事項の確認
→ その後の手続きで使用するため、変更内容を反映した住民票を取得しておくと便利
必要書類の例
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
- 転出証明書(別の市区町村から引っ越す場合)
- 印鑑(自治体によって不要な場合もあり)
これらの手続きは、結婚に伴って姓や住所が変更になる場合がほとんどなので、同時に済ませることで効率よく進められます。
なお、住民票の変更が完了していないと、銀行や保険など他の名義変更にも影響が出るため、最優先で対応しましょう。
入籍後やることリスト①|保険・年金・マイナンバーの名義変更
結婚に伴い氏名や住所が変わる場合、保険・年金・マイナンバー関連の名義変更も忘れずに行いましょう。
これらは公的制度に関わる重要な手続きで、正しく変更しておかないと後々トラブルになる可能性もあります。
国民健康保険・社会保険の変更
- 自営業や無職の場合:市区町村で国民健康保険の住所・氏名変更を申請
- 会社員の場合:勤務先を通じて社会保険の氏名・扶養情報の変更を申請
※扶養に入る場合は、保険証の発行までに1〜2週間かかることもあるため、早めの申請が必要です。
国民年金・厚生年金の手続き
- 国民年金加入者は、市区町村の窓口で住所・氏名変更の届け出
- 厚生年金加入者は、会社側で変更手続きを行うため、必要書類を早めに提出しましょう
マイナンバーカードの変更
- 氏名や住所が変わった場合は、14日以内に市区町村窓口で変更手続きが必要
- カード自体の更新や、暗証番号の再設定が必要になることも
これらの手続きは、他の名義変更の際に身分証明として必要になるケースが多いため、優先的に対応するのがおすすめです。
入籍後やることリスト①|運転免許証やパスポートの変更も忘れずに
結婚によって氏名や住所が変わった場合、運転免許証やパスポートの情報も早めに変更しておく必要があります。
これらは身分証明書として使用する機会が多いため、更新を後回しにすると不便を感じる場面が出てきます。
運転免許証の変更
- 変更内容:氏名・住所のいずれか、または両方
- 手続き場所:最寄りの警察署または運転免許センター
- 必要書類:
- 旧免許証
- 新しい住所・氏名を証明できる書類(住民票やマイナンバーカードなど)
- 結婚後の新姓が確認できる書類(婚姻受理証明書など)
- 旧免許証
※免許証は他の手続きの際の本人確認にも使われるため、早めの変更がおすすめです。
パスポートの変更(氏名・本籍地など)
- 手続き方法:都道府県のパスポートセンターで「記載事項変更申請」
- 必要書類:
- 現在のパスポート
- 戸籍謄本(6ヶ月以内のもの)
- 顔写真(規定サイズ)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 現在のパスポート
※新婚旅行を控えている人は要注意。旧姓のまま航空券を予約している場合は、変更せずに渡航するほうがスムーズなこともあります。
これらの公的証明書は、あらゆる場面で必要になる大切な書類です。引っ越しや他の名義変更とタイミングを合わせて、効率よく進めましょう。
入籍後やることリスト①|銀行口座の名義・住所変更も早めに対応
結婚に伴って姓や住所が変わった場合、銀行口座の名義・住所変更も早めに済ませておくことが重要です。
特に、給与振込や公共料金の引き落としに使っている口座は、変更を怠ると後々トラブルの原因になることがあります。
変更が必要なタイミング
- 住民票やマイナンバーの情報が更新された後
- 結婚後の姓で通帳やキャッシュカードを利用する場合
- 各種手続きや引き落としに正しい名義が必要な場合
手続きの流れ
- 窓口に直接行くのが基本(一部ネットバンクではオンライン対応あり)
- 必要書類:
- 通帳・キャッシュカード
- 新姓・新住所が確認できる本人確認書類(住民票・免許証など)
- 届出印(印鑑が必要な銀行の場合)
- 通帳・キャッシュカード
※複数の口座がある場合は、リストを作ってまとめて対応すると手間が省けます。
ネットバンク・ゆうちょ銀行の場合
- ネットバンクでは、本人確認書類のアップロードで手続き完了できるケースもあります
- ゆうちょ銀行は窓口での対応が必要ですが、土曜対応窓口もあるため事前に確認を
銀行口座の情報は、クレジットカードや携帯料金など他の支払いと連動していることも多いため、早めに正しい情報へ更新しておくのが安心です。
入籍後やることリスト②|【勤務先での手続き】も忘れずに

入籍後は、役所だけでなく勤務先への報告や各種手続きも必要です。
氏名や住所の変更にともなって、社内書類の更新や扶養申請などが求められるほか、退職や働き方を見直すケースもあります。
ここでは、職場でスムーズに対応するためのポイントを、状況別に整理して解説します。
入籍後やることリスト②|会社への届け出のタイミングとマナー
結婚後は、勤務先への報告と各種手続きの届け出も必要になります。
報告のタイミングやマナーを押さえておくことで、スムーズかつ印象の良い対応が可能です。
いつ、誰に報告する?
- 報告のタイミング:入籍が完了したら、できるだけ早めに(遅くとも1週間以内が目安)
- 報告する相手:まずは直属の上司に口頭で伝えるのが基本
- 上司への報告後、必要に応じて人事部門などへ書類を提出する
報告時のマナー
- 勤務時間内の落ち着いたタイミングで報告
- 「私事で恐縮ですが」と前置きし、結婚の事実と入籍日を伝える
- 今後の姓や住所の変更についてもあわせて説明しておくと親切
書類提出・手続きの例
- 扶養申請や住所変更届の提出
- 氏名変更に伴う社内システムやメールアドレスの更新
- 通勤手当や福利厚生の再申請が必要になることも
職場によって手続きの流れが異なる場合があるため、早めに上司に相談し、必要な書類や期限を確認しておくと安心です。
入籍後やることリスト②|扶養や名字変更に伴う必要書類とは
結婚後に勤務先で行う手続きの中でも、扶養に関する申請や名字変更の届け出には特定の書類が必要です。
スムーズに進めるために、あらかじめ必要書類を確認・準備しておきましょう。
扶養申請に必要な書類(健康保険・税務関連)
- 健康保険被扶養者異動届(会社の指定フォーマット)
- 婚姻関係がわかる書類(戸籍謄本や婚姻受理証明書)
- 扶養対象者の所得証明書や課税証明書(必要な場合)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
※扶養条件(収入など)を満たすかどうかも合わせて確認が必要です。
名字変更の手続きに必要な書類
- 社員情報変更届や氏名変更届(企業により名称は異なる)
- 新しい氏名の記載された本人確認書類(住民票・マイナンバーカードなど)
また、社内で使用しているメールアドレス・名札・名刺・人事システムなども、変更が必要になることがあります。
これらの更新タイミングも、上司や人事部門に確認しておくと安心です。
企業によって申請方法や書類のフォーマットが異なるため、まずは社内規定や担当窓口に問い合わせて確認するのが確実です。
入籍後やることリスト②|結婚・引っ越しによる名刺・住所変更
結婚や引っ越しに伴って、職場で使用する名刺や社内情報の住所・氏名を変更する必要があります。
外部とのやり取りが多い職種ほど、早めに対応しておくことでトラブルを防げます。
名刺の変更
- 名字が変わった場合は必ず名刺の再発行を依頼
- 旧姓を残すかどうかは会社の方針によるが、「新姓(旧姓)」という表記が可能な場合もある
- 名刺交換の場では、「このたび結婚しまして、姓が変わりました」と一言添えると丁寧
住所・連絡先の変更
- 社内システムや人事データベースの住所更新
- 社外用の資料や署名欄の連絡先情報の変更
- 社内で使用している郵便物の送付先や通勤定期券情報の見直し
周囲への周知
- 同僚や関係部署へ、新しい氏名・住所に変更したことをメールや口頭で伝える
- クライアント対応をしている場合は、あらかじめ変更の連絡をしておくと親切
名刺や住所などの変更は後回しにしがちですが、情報のズレが業務に支障をきたすこともあるため、優先的に対応しましょう。
入籍後やることリスト②|退職する場合と配偶者の扶養に入る場合の手続き
結婚を機に退職を考えている場合や、配偶者の扶養に入る場合は、通常の結婚手続きとは別の追加対応が必要です。
それぞれのケースに応じて、必要な手続きと書類を整理しておきましょう。
結婚を機に退職する場合
- 退職届の提出:提出期限やフォーマットは職場ごとに異なるため、就業規則を確認
- 健康保険・年金の切り替え:
- 自営業・無職になる場合 → 国民健康保険・国民年金に加入手続き
- 配偶者の扶養に入る場合 → 配偶者の勤務先を通じて申請が必要
- 自営業・無職になる場合 → 国民健康保険・国民年金に加入手続き
- 退職後の保険証の返却や雇用保険の手続き(ハローワーク)も忘れずに
配偶者の扶養に入る場合
- 扶養申請書の提出(配偶者の勤務先で用意)
- 必要書類:
- 戸籍謄本や婚姻受理証明書
- 扶養に入る人の所得証明書・無職証明書など
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 戸籍謄本や婚姻受理証明書
※収入の条件(年収130万円未満など)を満たしている必要があるため、事前に要件を確認しておくことが大切です。
これらの手続きは、夫婦双方の勤務状況や生活スタイルによって変わるため、早めに相談・準備を進めておくことでスムーズに対応できます。
入籍後やることリスト③|【家族・親戚・友人】への挨拶や報告

入籍後は、家族や親戚、友人など、周囲の人への挨拶や報告も欠かせません。
タイミングや伝え方によっては相手に気を遣わせてしまうこともあるため、丁寧な対応が求められます。
このセクションでは、家族・親戚・友人それぞれへの伝え方のマナーや、お知らせの手段について解説します。
入籍後やることリスト③|入籍後の家族への挨拶マナー
入籍を終えたら、お互いの家族への挨拶や報告を丁寧に行うことが、今後の良好な関係づくりにつながります。
形式ばらずとも、感謝の気持ちを伝える姿勢が大切です。
挨拶の基本マナー
- 入籍後、できるだけ早めに訪問するのがベスト(1週間〜10日以内が目安)
- 相手の都合を確認し、日時を調整してから伺う
- 堅苦しくなりすぎず、「今後ともよろしくお願いします」の気持ちを込めて伝える
手土産の選び方
- 地元の名産や、相手の好みに合わせたお菓子などが一般的
- 2,000〜3,000円程度が目安(高価すぎるものはかえって気を遣わせる)
- 挨拶と一緒に渡し、「お口に合えばうれしいです」と一言添えると好印象
挨拶の流れ(例)
- 「このたび○○さんと入籍しましたので、ご挨拶に伺いました」
- 軽く会話をしつつ、結婚生活への意気込みや近況を報告
- 今後の予定(新居や仕事、式の計画など)を共有するのもおすすめ
入籍後の挨拶は、義務というより「感謝とけじめ」の気持ちを表す場です。丁寧で誠実な対応が、信頼関係を築く第一歩となります。
入籍後やることリスト③|年賀状やお知らせのタイミング
入籍後の報告を、年賀状や結婚報告はがきで伝えるケースも増えています。
フォーマルすぎず、相手に気を遣わせない方法として、年賀状での報告は非常に便利です。
年賀状で入籍報告する場合
- タイミング:入籍の翌年の正月(1月1日着)に届くように
- メッセージ例:
- 「私たちは○月○日に入籍いたしました」
- 「今後とも変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします」
- 「私たちは○月○日に入籍いたしました」
- 写真入りデザインも人気(ただし相手に応じて選ぶこと)
結婚報告はがきを送る場合
- タイミング:入籍から1ヶ月以内が目安(年賀状を送らない相手に向けて)
- 送る相手:
- 遠方に住む親戚や疎遠になっている友人
- 結婚式に招待しなかった人などにおすすめ
- 遠方に住む親戚や疎遠になっている友人
- 文例には、入籍日・新居の住所・連絡先などを含めると親切
注意点
- 喪中の相手には年賀状ではなく、寒中見舞いや報告はがきで対応するのがマナー
- 形式にこだわりすぎず、「感謝とご挨拶の気持ち」が伝わる文面を心がける
年賀状やはがきでの入籍報告は、堅苦しくなく、相手にも気を遣わせない自然な方法として人気です。
準備に少し時間がかかるため、早めにデザインや文面を考えておくと安心です。
入籍後やることリスト③|友人・知人への報告の仕方
入籍後は、家族や親戚だけでなく、友人や職場の同僚など身近な人たちにも結婚の報告をすることが大切です。
報告の仕方は相手との関係性や距離感に合わせて柔軟に選びましょう。
直接会える場合
- 食事や集まりの場で自然に報告
- タイミングは、会話が落ち着いた頃に「実は、○月に結婚しました」と伝える
- 一緒にお祝いしてもらえる場があると、今後の関係もより深まります
会えない場合・遠方の友人
- LINEやメールでの報告が一般的
- 文面例:
- 「ご報告です。○月○日に入籍しました!今後ともよろしくね」
- 写真付きで送ると、雰囲気が伝わって好印象に
- 「ご報告です。○月○日に入籍しました!今後ともよろしくね」
SNSを活用する場合
- FacebookやInstagramでの投稿は、タイミングに注意
- まずは親しい人への個別報告を済ませてから全体へ投稿するのがマナー
- 写真やコメントは、自分たちのスタイルに合ったものにまとめてOK
報告の順番や伝え方に配慮することで、相手に対して誠実な印象を与えることができます。
特に仲の良い友人には、形式よりも気持ちが伝わるような言葉を選ぶのがおすすめです。
入籍後やることリスト④|【引っ越しに関する手続き】をスムーズに

結婚を機に新居へ引っ越す場合は、住所変更にともなう各種手続きが発生します。
役所への届け出だけでなく、ライフラインや通信環境、郵便物の転送など、忘れがちな項目も多くあります。
このセクションでは、引っ越し後の生活をスムーズに始めるために必要な手続きを、順を追って整理して解説します。
入籍後やることリスト④|転出届・転入届の手続き
結婚にともなって引っ越す場合は、住民票の移動に関する手続き(転出届・転入届)が必要です。
これらは法律で提出期限が定められており、他の公的手続きの土台にもなるため、早めに対応しておきましょう。
手続きの基本
- 転出届:引っ越し「前」に現在の市区町村へ提出
- 転入届:引っ越し「後」に新住所の市区町村で提出
- 提出期限:
- 転出届:引っ越す日まで
- 転入届:引っ越した日から14日以内
- 転出届:引っ越す日まで
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(自治体によっては不要)
- 転出証明書(転入時に必要)
- 住民異動届(自治体の様式あり)
- マイナンバーカードまたは通知カード
手続きの流れ
- 旧住所の役所で転出届を出す(転出証明書を受け取る)
- 新住所の役所に転入届を出す(転出証明書を持参)
- 必要に応じて、世帯主変更・印鑑登録・マイナンバーの更新も行う
住民票の情報は、免許証や銀行・保険などの名義変更にも影響します。
入籍と引っ越しのタイミングが近い場合は、スケジュールを整理して手続きの重複を避けましょう。
入籍後やることリスト④|電気・ガス・水道などライフラインの契約変更
引っ越しに伴って必要になるのが、電気・ガス・水道などライフラインの契約変更手続きです。
これらは生活に直結するため、移転前後のタイミングで確実に対応することが重要です。
ライフラインごとの基本的な流れ
- 電気の手続き
- 旧居:使用停止の申し込み(引っ越し日までに)
- 新居:使用開始の申し込み(引っ越し前日までに)
- 電力会社にWebまたは電話で連絡
- 旧居:使用停止の申し込み(引っ越し日までに)
- ガスの手続き
- 旧居:使用停止の申し込み
- 新居:使用開始の立ち会いが必要(都市ガスの場合)
- ガス会社に早めの予約を
- 旧居:使用停止の申し込み
- 水道の手続き
- 旧居:使用中止の届け出
- 新居:使用開始の申し込み
- 地域の水道局に連絡(多くはネット受付可)
- 旧居:使用中止の届け出
連絡時に必要な情報
- 契約者名
- 現住所・新住所
- 引っ越し予定日・開始希望日
- 電気・ガス・水道の「お客様番号」や「契約番号」(検針票に記載)
注意点
- 新居での開始日を引っ越し当日に設定し忘れると、生活に支障が出ることも
- 使用停止・開始の連絡は引っ越しの1週間前までには済ませるのが理想
これらのライフライン手続きは、タイミングと順番を間違えないことがポイントです。ToDoリストを作って、もれなく対応しましょう。
入籍後やることリスト④|インターネット・固定電話・NHKの変更手続き
引っ越しにともなって、インターネット回線や固定電話、NHKの契約住所の変更も必要になります。
特にインターネットは日常生活に欠かせないため、早めの対応がカギになります。
インターネット回線の変更手続き
- 光回線・ケーブル回線などの場合
→ 現在の契約を「移転」するか、「解約→新規契約」にするかを選択 - 手続きの流れ:
- プロバイダーや回線業者へ連絡
- 工事日を予約(引っ越し前後で調整)
- 機器の返却・設置作業
- プロバイダーや回線業者へ連絡
※工事の混雑により1〜2週間待つケースもあるため、引っ越しが決まったらすぐに連絡を。
固定電話の手続き
- 使用している場合は、NTTなどのサービスに住所変更を届け出
- 番号をそのまま引き継げるかどうかは、地域や契約によって異なる
NHKの住所変更
- NHK公式サイトまたは電話で手続き
- 受信契約は引き続き有効となるため、転居先の情報を伝える必要あり
- 支払い方法に変更がある場合は、あわせて更新を
これらの手続きは、生活インフラと密接に関わるため後回しにしないことが大切です。
ネットや電話の使用開始が遅れると、生活や仕事に支障が出る可能性もあるため、引っ越し前に段取りを整えておきましょう。
入籍後やることリスト④|郵便物の転送届や宅配登録情報の更新も忘れずに
引っ越し後の住所変更では、郵便物や宅配便の登録情報の更新も見落としがちです。
大切な書類や荷物を確実に受け取るために、早めに手続きをしておきましょう。
郵便物の転送届(日本郵便)
- 転送届を出しておくと、旧住所宛の郵便物が1年間新住所へ転送される
- 提出方法:
- 郵便局の窓口(本人確認書類が必要)
- 日本郵便の公式サイトからオンライン申請も可能
- 郵便局の窓口(本人確認書類が必要)
- 住所変更が完了していないタイミングでも、先に転送届を出せるので安心
宅配業者の登録情報変更
- ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便(ゆうパック)など
→ 会員登録している場合は、マイページから住所情報を更新 - Amazon・楽天など通販サイトの「お届け先」登録も変更を忘れずに
更新を忘れやすいサービス
- フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)
- 定期購入やサブスクサービス(食品・コスメなど)
- 銀行・クレジットカード会社の「明細送付先」や「通知先」
郵便物や荷物が旧住所に届いてしまうと、再送依頼やトラブルの原因になりかねません。
生活の中で使っているサービスの登録情報は、チェックリストでまとめて見直すと漏れを防げます。
入籍後やることリスト⑤|【氏名・住所変更が必要な民間サービスの手続き】
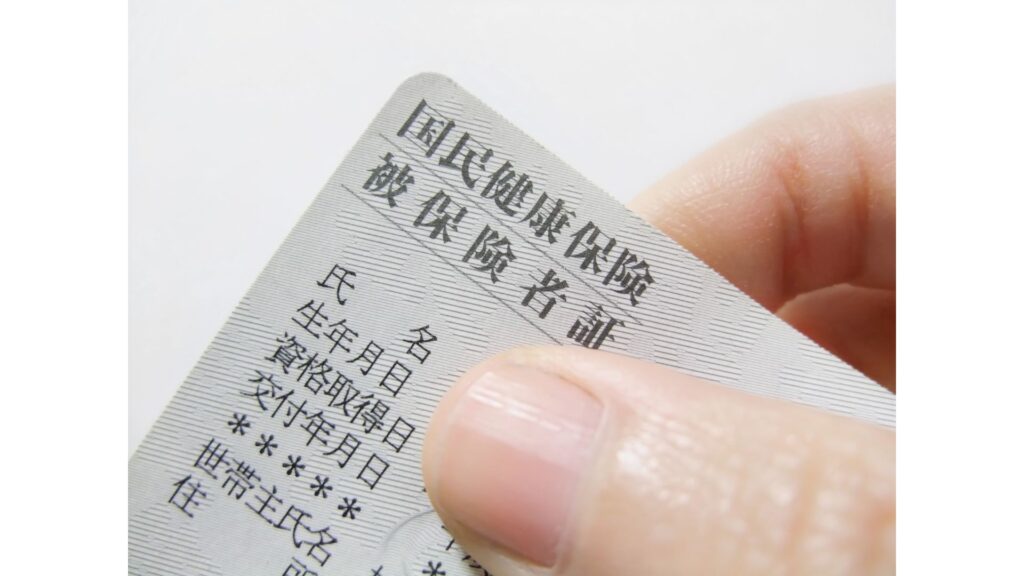
入籍後は、氏名や住所の変更にともない、クレジットカードや携帯電話、各種ネットサービスなど、民間サービスの登録情報も見直す必要があります。
手続きを後回しにすると、配送ミスや決済エラーの原因になることも。ここでは、生活に関わる主要なサービスの変更ポイントを整理して紹介します。
入籍後やることリスト⑤|クレジットカードや保険の名義変更
結婚後に姓や住所が変わった場合、クレジットカードや各種保険の名義変更も早めに行う必要があります。
本人確認や支払い情報に関わるため、放置すると利用制限やトラブルにつながることもあります。
クレジットカードの名義・住所変更
- 手続き方法:
- 各カード会社の会員サイトにログインして、氏名・住所を変更
- カード裏面の電話番号に連絡して申請する方法もあり
- 各カード会社の会員サイトにログインして、氏名・住所を変更
- 注意点:
- 新しい名字のカードが再発行される場合、手元に届くまで1〜2週間かかる
- 古いカードは破棄せず、新カード到着後に処分するのが安心
- 新しい名字のカードが再発行される場合、手元に届くまで1〜2週間かかる
保険(生命保険・医療保険など)の名義変更
- 保険会社のコールセンターや担当者に連絡し、変更手続きの書類を取り寄せ
- 氏名・住所の変更のほか、受取人の変更が必要になることも
- 変更後の保険証券は、再発行されるケースが多いため保管場所を確認
変更時に必要な情報
- 契約者番号や証券番号
- 新しい姓・住所
- 必要に応じて、住民票や婚姻受理証明書などの提出
金融や保険に関する情報は、第三者へのなりすまし防止のために慎重な確認が求められます。
変更漏れを防ぐため、使っているカードや保険の一覧を作ってチェックしながら進めましょう。
入籍後やることリスト⑤|携帯電話の契約名義や住所の変更
結婚後は、携帯電話の契約者情報(氏名・住所)の変更手続きも忘れずに行いましょう。
月々の請求書や重要な通知が届くため、登録情報を正確にしておくことが大切です。
主な携帯会社での変更方法
- docomo / au / SoftBank / 楽天モバイルなど大手キャリア
→ オンライン(マイページ)またはショップ窓口で手続き可能 - 格安SIM(MVNO)各社(UQモバイル、Y!mobileなど)
→ Web手続きが中心。本人確認書類のアップロードが必要な場合あり
変更に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 登録済みの4桁の暗証番号(ショップでの手続き時に必要な場合あり)
- 新しい住所が確認できる書類(住民票、公共料金の領収書など)
手続きの注意点
- 名字が変わると、契約者名義として再登録されるケースもある
- 支払い名義のクレジットカードも同時に変更するとスムーズ
- 家族割やシェアプランを組んでいる場合、影響が出ることもあるので事前に確認を
携帯電話は毎日使うものだからこそ、登録情報を正しく保つことでトラブルを防ぎ、安心して利用できます。
住所変更とあわせて、忘れずに手続きを済ませておきましょう。
入籍後やることリスト⑤|通販サイト・オンラインサービスの登録情報変更
結婚や引っ越しにともない、通販サイトやオンラインサービスの登録情報も更新しておくことが必要です。
住所や氏名の変更を忘れると、商品が届かない・本人確認ができないなどのトラブルにつながる可能性があります。
代表的な通販サイトの変更項目
- Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング
→ ログイン後、アカウント設定から以下を更新:
- 登録氏名
- お届け先住所
- 支払い方法(クレジットカードの名義や有効期限も確認)
- 登録氏名
- ZOZOTOWN・メルカリ・ラクマなどの個人売買サービス
→ 購入・発送ともにトラブルが起きやすいため、早めの変更を
サブスクリプション・定期便サービス
- 食材宅配(Oisix、ヨシケイなど)
- 美容・コスメ系の定期便
- 動画・音楽ストリーミング(Netflix、Spotifyなど)
→ 住所だけでなく、支払いカードの名義が変わる場合は登録更新が必要
注意点
- 一部サービスでは本人確認が必要になる場合がある(住民票や免許証など)
- アプリから変更できるものと、PCでのログインが必要なものがあるため、事前に確認しておくとスムーズ
毎日利用しているサービスほど登録情報の変更を見落としがちなので、利用頻度の高い順にチェックリストを作って一つずつ更新していくのがおすすめです。
入籍後やることリスト⑤|新婚旅行を控えている場合のパスポート手続きに注意
新婚旅行を計画している場合、パスポートの氏名変更には注意が必要です。
航空券やホテルの予約に使う名前と、パスポートに記載された名前が一致していないと、渡航に支障をきたすことがあります。
氏名変更は必須ではない
- 入籍後も、旧姓のままのパスポートは有効です(有効期限内であれば使用可能)
- すでに旧姓で航空券を予約している場合は、パスポートも旧姓のままでOK
- ただし、滞在先での身分証明が必要なケースでは、新姓と一致していないとトラブルになる可能性も
氏名を変更したい場合の手続き
- 申請方法:パスポートセンターで「記載事項変更申請」を行う
- 必要書類:
- 戸籍謄本(6ヶ月以内)
- 顔写真(縦45mm×横35mm)
- 現在のパスポート
- 本人確認書類(免許証など)
- 戸籍謄本(6ヶ月以内)
- 手数料:約6,000円前後(都道府県により異なる)
注意点
- 新しいパスポートが手元に届くまでに1週間程度かかる
- 氏名を変更した場合、航空券の名前変更も必要になることがある(航空会社によっては変更不可)
- 海外旅行後にパスポートを更新するという選択肢もあり
パスポートと航空券の氏名が一致していることが最優先なので、結婚のタイミングと旅行のスケジュールを照らし合わせて手続きを判断しましょう。
入籍後やることリスト⑥|【今後の準備・ライフプラン】も忘れずに

入籍後の生活をより豊かにしていくためには、今後のライフプランについてもしっかり話し合っておくことが大切です。
結婚式や新婚旅行の予定、新居の準備、妊活や仕事のバランスなど、夫婦で共有すべきテーマはさまざまです。
このセクションでは、将来を見据えた準備について整理して紹介します。
入籍後やることリスト⑥|結婚式や新婚旅行のタイミングは?
入籍後に控えているイベントとして代表的なのが、結婚式と新婚旅行です。
スケジュールの組み方次第で、準備の負担や手続きのタイミングも大きく変わるため、計画的に進めることが大切です。
結婚式のタイミング例
- 入籍前に結婚式を挙げる場合
→ 招待状や式場での表記は旧姓を使用することが多い
→ 入籍日は「式の前日」や「大安・記念日」などを選ぶケースが多い - 入籍後に結婚式を挙げる場合
→ 氏名変更や住所変更が完了しているため、手続きがスムーズ
→ 準備期間に余裕ができるというメリットも
新婚旅行のタイミング例
- 結婚式直後に行くパターン(ハネムーン)
→ 旅行先の気候や季節、仕事の都合なども考慮して決定
→ パスポートや航空券の氏名に注意(旧姓か新姓かを統一) - 数ヶ月後に時期をずらして行くパターン
→ 予算や日程を調整しやすく、オフシーズンを狙って旅費を抑えることも可能
スケジューリングのポイント
- 結婚式と旅行の間に余裕を持たせると、体調や準備の負担を軽減できる
- 手続きや名義変更が絡むため、入籍日・式日・旅行日をセットで計画すると効率的
ライフイベントが続く時期だからこそ、無理のないスケジュールと事前準備が安心なスタートの鍵になります。
入籍後やることリスト⑥|新居・引っ越しの準備と優先順位
結婚を機に新居を構える場合、引っ越しに関する準備や優先順位の整理が必要になります。
物件探しから生活環境の整備まで、やることは多いですが、段取りよく進めることでスムーズな新生活を迎えられます。
引っ越し前にやるべきこと
- 新居探し:家賃・立地・通勤距離・間取りなどの条件をすり合わせ
- 契約手続き:契約日と引っ越し日を明確に設定し、重ならないよう調整
- 引っ越し業者の手配:繁忙期(3〜4月、9月)を避けると費用を抑えやすい
- 不用品の処分・荷造り:断捨離のチャンスでもあるため、早めに取りかかるのがおすすめ
引っ越し後にやるべきこと
- ライフラインの使用開始手続き(電気・ガス・水道)
- インターネット回線やNHKの契約変更
- 家具・家電の設置と生活導線の確保
優先順位の決め方
- 生活に直結するものから着手(ライフライン、寝具、調理器具など)
- 時間がかかる手続き(ネット回線の開通、住民票の変更など)は早めに申請
- 家具・家電は、必要最低限から始めて住んでから買い足すのも◎
新居の準備はふたりで暮らすための第一歩。お互いのこだわりや生活リズムをすり合わせながら進めることが、結婚生活のよいスタートになります。
入籍後やることリスト⑥|妊活・仕事の今後についての話し合い
入籍を機に、新しい生活が始まる中で、妊活や仕事に関する今後の方向性を夫婦で話し合っておくことも大切です。
今すぐ行動に移すかどうかに関係なく、価値観や優先順位を共有しておくことで、後々のすれ違いを防げます。
話し合っておきたいテーマ例
- 妊活・子どもを持つタイミング
- いつ頃を目安に考えているか
- 不妊治療の可能性や健康面での不安があるか
- 子どもを持たない選択も含め、考え方をすり合わせる
- いつ頃を目安に考えているか
- 仕事とのバランス
- 今後も共働きを続けるか、一時的にどちらかがセーブするか
- 転職・在宅勤務・時短勤務などの希望
- 転勤や転居を伴う異動への対応方針
- 今後も共働きを続けるか、一時的にどちらかがセーブするか
- 家事・育児の分担
- 現時点での役割分担と、今後の想定
- 家事代行サービスの利用なども含めた現実的な線引き
- 現時点での役割分担と、今後の想定
話し合うタイミングの工夫
- 引っ越しや結婚式の落ち着いたタイミングにゆっくり話す
- 書き出しながら整理することで、意見のすり合わせがしやすくなる
- 無理に結論を出さず、定期的に見直すスタンスでもOK
結婚後のライフプランは、「今」だけでなく「これから」を見据えた準備の第一歩です。
安心して暮らしていくために、まずはふたりで気軽に話し合う時間を持つことが大切です。
入籍後やることリスト⑦|結婚式は入籍前?後?ベストなタイミングとは

結婚式と入籍のタイミングは、カップルによってさまざまです。
式を先に行うか、入籍を先にするか、あるいは同じ日にまとめるか、それぞれにメリットがあります。
どの順番が正解というわけではなく、自分たちに合ったスタイルを選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれのタイミングの特徴と選び方を解説します。
入籍後やることリスト⑦|入籍前に結婚式をするメリット
入籍と結婚式の順番はカップルによってさまざまですが、入籍前に結婚式を挙げるスタイルには、準備や演出の面で特有のメリットがあります。
旧姓のままで統一できる点や、手続きの時期をずらせることで負担を軽減できるなど、合理的な理由で選ばれるケースも多くあります。
メリット①:旧姓のまま式を挙げられる
- 招待状や席次表、誓約書などを旧姓で統一できる
- ゲストも呼び慣れた名前で接しやすく、違和感が少ない
- 氏名変更の手続き前なので、各種準備がスムーズに進む
メリット②:名義変更を後回しにできる
- 入籍後だと、新姓で予約を取り直したり、身分証明の確認に手間がかかる場面も
- 入籍を式の後にすれば、すべて旧姓で統一でき、準備や手続きが煩雑になりにくい
- 結婚式に集中したい人にとって、スケジュールの分散は大きなメリット
メリット③:式で両家へ感謝を伝えた後に入籍できる
- 結婚式を通して、両親や親族にこれまでの感謝を伝えた上で、入籍という“けじめ”を迎えられる
- 「儀式→手続き」という流れに安心感を覚える人も多い
- 形式を重んじる家庭にとって、自然なステップとなる
入籍前に結婚式を行うスタイルは少数派ではありますが、自分たちのペースで準備を進めたいカップルや、旧姓で思い出を残したい人にとっては魅力的な選択肢です。
入籍後やることリスト⑦|入籍後に結婚式をするメリット
現在は、「入籍後に結婚式を挙げる」スタイルがもっとも一般的とされています。
ゼクシィの調査(2023年)によると、全体の約9割のカップルが、結婚式よりも先に入籍を済ませており、この順序を選ぶカップルが主流です。
メリット①:名義や身分証の変更を済ませてから準備できる
- 氏名変更が終わっているため、式場・宿泊・旅行などの予約も新姓で統一可能
- 書類や契約のトラブルを回避でき、事務手続きがスムーズ
- 新姓での生活に慣れてから式を迎えられるため、安心感もある
メリット②:結婚生活の実感を持ちながら式を迎えられる
- 実際に夫婦としての生活を経験していることで、式の誓いにリアリティが増す
- 共同生活を通して、お互いの価値観や希望を式の準備に反映しやすい
- 式の段取りや役割分担もスムーズに行えるようになる
メリット③:ライフプランに合わせて柔軟にスケジュールが組める
- 仕事や妊娠・出産のタイミングに合わせて、無理のない日程を選べる
- 費用の貯蓄や式場の選定に時間をかけられる
- 「とりあえず入籍だけ済ませて、落ち着いたら式を挙げたい」という人にも最適
入籍後に結婚式を行うスタイルは、現実的・合理的で、今の時代に合った流れといえます。
生活を整えたうえで落ち着いて式に臨みたいカップルには、とても人気のある順序です。
入籍後やることリスト⑦|入籍日と結婚式を同じ日にするメリット
入籍と結婚式を別日にするカップルが多い中で、同じ日にまとめて行うスタイルを選ぶ人も一定数います。
手続きとセレモニーを1日に集中させることで、記念日としての特別感がより高まるというメリットがあります。
メリット①:一生に一度の記念日をひとつにできる
- 入籍と挙式が同じ日であれば、「結婚記念日=式の日」として毎年わかりやすくお祝いできる
- 日付がひとつにまとまることで、忘れにくく、毎年の思い出も一層濃くなる
- 夫婦で過ごす節目として、自然に意識しやすくなる
メリット②:特別な日として演出しやすい
- 大安や語呂の良い日など、縁起の良い日を選ぶことで、より意味を持たせられる
- 「今日から夫婦です」とゲストに伝えられるため、祝福の気持ちも一層強くなる
- セレモニーと法的な手続きを重ねることで、気持ちにもメリハリが生まれる
メリット③:スケジュールを1日で完結できる
- 入籍と挙式を別々に準備する必要がなく、段取りや準備の管理がシンプルになる
- 手続きや式の準備を同時進行で行えるため、日程や時間を効率よく使える
- 結婚という節目を1日で迎えることで、達成感や充実感も得やすい
ただし、役所の開庁時間と式の開始時間をうまく調整する必要があるため、事前にスケジュールをしっかり立てておくことがポイントです。
入籍後やることリスト⑦|結婚式と入籍のタイミングを決めるポイント
結婚式と入籍、どちらを先にするか—or 同じ日にするか。
正解はなく、ふたりの価値観やライフスタイルに合った順番を選ぶことが大切です。
以下にそれぞれの特徴をまとめたうえで、選び方のヒントを紹介します。
入籍前に結婚式をする人に向いているのは…
- 旧姓で式を挙げたい
- 準備や段取りにしっかり時間をかけたい
- セレモニーを「けじめ」にしたい
→ 氏名変更や手続きのタイミングを後ろ倒しにできるので、準備に集中したい人におすすめです。
入籍後に結婚式をする人に向いているのは…
- 現実的に手続きを早く済ませたい
- 引っ越しや扶養申請など、生活基盤を先に整えたい
- 落ち着いて式を準備したい
→ 書類や名義の統一がしやすく、事務的な混乱を避けたい人にぴったりです。
入籍と結婚式を同じ日にする人に向いているのは…
- 記念日をひとつにまとめたい
- 特別な日として強く印象に残したい
- スケジュールをシンプルにしたい
→ 演出の統一感や節目としての意味合いを重視したい人に適しています。
「どれが正解か」ではなく、ふたりにとって何を大事にしたいかを話し合うことが、後悔しない選び方につながります。
入籍後の思い出を残すなら?bellbouquet(ベルブーケ)という選択

入籍という特別な日を、記憶だけでなく「かたち」に残したいと考える人が増えています。
特に、プロポーズや入籍祝いでもらった花を記念品に残すアフターブーケの需要が高まる中、注目されているのがbellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドルです。
ここでは、その魅力と活用シーンを紹介します。
入籍の記念に残したい「思い出の花」

入籍という特別な節目には、ふたりの記憶をかたちに残すアイテムとして、プロポーズや記念日でもらった花束を保存する人が増えています。
中でも「アフターブーケ」と呼ばれる保存加工サービスは、注目度が高まっており、人気の選択肢となっています。
入籍と関わりの深い“思い出の花”とは?
- プロポーズのブーケ:ふたりの始まりを象徴する花
- 入籍祝いの花束:家族や友人からの祝福の気持ちがこもっている
- 新居に飾った花:新生活のスタートを彩る存在
これらの花は、見た目の美しさだけでなく、その時の気持ちや空気感までも呼び起こしてくれる大切な記憶です。
ただ枯れてしまうのを待つのではなく、加工によって長く残せば、見るたびに幸せな気持ちがよみがえります。
近年では、インテリア性や実用性も兼ね備えた「ブーケキャンドル」など、新しい形のアフターブーケも登場しており、おしゃれに、そして自然に日常に馴染む記念のかたちとして選ばれています。
入籍記念にもぴったりなbellbouquetの魅力とは

入籍という人生の節目を、ただの思い出で終わらせず、美しいかたちで残したい。
そんな願いに応えるのが、bellbouquet(ベルブーケ)のブーケキャンドルです。
お花の魅力を最大限に活かしながら、暮らしに自然に馴染む“アートな記念品”として注目されています。
bellbouquetのブーケキャンドルはここが違う
- 外側に透明なパラフィンワックスを使用し、花の色や形を立体的に保存
- 中央にはアロマ入りのキャンドルを内蔵
→ 香りを楽しむことができ、インテリアにも実用品としても優れる - アトリエで1点ずつ手作業で仕上げる完全オーダーメイド
→ 自分たちだけの特別な1本に仕上がる
実用性・保存性・インテリア性をすべて備えたアイテム
- ワックスで密閉されているため、外気や湿気に強く、劣化や色褪せが起きにくい
- ガラスではないため割れにくく、型崩れもしにくい安心設計
- 玄関・リビング・寝室など、どこに飾っても映える高いインテリア性
- 香りを楽しめる実用性を備えており、“見るだけ”では終わらない
これらすべての要素を兼ね備えているからこそ、bellbouquetのブーケキャンドルは、
「実用性×インテリア性×思い出の保存」が融合した、唯一無二のアフターブーケなのです。
大切なブーケを”一生の思い出”
に残す方法をご存じですか?
👰「結婚式で使ったブーケ、捨てるのはもったいない…」
💐「大切な花束を、形として長く残していたい…」
😭「料金や保存期間が心配だけど、どこに相談したらいいかわからない…」
ブーケは結婚式の思い出そのもの。でも、「どこに頼めばいい?」「デザインは?」「費用は?」など不安はつきものですよね。

bellbouquet(ベルブーケ)は、累計2,000本以上の花嫁様の“アフターブーケ”をサポートしてきたアフターブーケキャンドル専門店です。
今なら公式LINEにご登録いただくだけで、「あなたのイメージに合うアフターブーケキャンドルとお見積り」を無料でご案内!
さらに、本記事限定で、「3,000円OFFクーポン」 をプレゼント中!
結婚式の大切な想い出を、“美しく、永く” 残してみませんか?
まとめ:入籍後のやることを知って、スムーズな新生活を
入籍後は、役所での手続きや勤務先への申請、家族や友人への報告など、やるべきことが一気に増えます。
住所や氏名の変更にともなう各種対応は、生活のあらゆる場面に関わってくるため、早めにスケジュールを立てておくことが大切です。
特に平日しかできない手続きは優先度が高く、1日でまとめて終わらせるための段取りも重要です。
また、新生活の準備だけでなく、結婚式や新婚旅行、仕事や妊活など、将来に向けた話し合いも欠かせません。
思い出を残す手段としてアフターブーケを活用するのもおすすめです
入籍後の流れを把握しておくことで、心にゆとりを持ちながら、ふたりらしい結婚生活をスタートさせることができます。